こんにちは。おちばです。
今回の記事で紹介するのは、「透析を止めた日」という本です。
医療従事者はもちろん、一般の方にも話題になっており、2025年3月時点でAmazonで320件のレビューで★4.4とかなり高評価になっております。
実際に読んでみて、とても読みやすい文章だったのに加え、医師として仕事をするうえで大切と思われる内容がちりばめられていました。
これはすべての腎臓内科医、いや、すべての医師が読んでおくべき必修本といえます。
透析を止めた日、まだ読んでる途中だけど、すごい。医師こそ読むべき本だと思う。
— おちば@腎臓内科 (@autumnleaveskid) February 7, 2025
水分制限、カリウム制限など透析患者さんが気にされてることが、患者さんの目線でリアルに伝わってくる。
分かってるつもりでも分かっていないことが多い。気をつけよう。#pr https://t.co/pgQnJ7baTX
今回の記事では、本の概要や感想、学んだことを述べていきたいと思います。
①透析患者の半生を、「妻」の目線でプロが描く
本書で取り上げられている症例は簡単にまとめると以下の通りです
常染色体優性多発性嚢胞腎(ADPKD)を原疾患とした末期腎不全の若年男性。テレビ局で働く凄腕のプロデューサーです。初めの数年間は血液透析が行われていましたが、途中で母親から腎移植を受けました。しばらくは透析離脱できていましたが、再度腎機能の悪化を認め、血液透析を再導入。最終的には腹水貯留や下肢壊疽が進行し、大学病院で緩和ケアを希望したものの叶わず、苦しみながら病院で亡くなられました。
この本の特筆すべきこと、それは透析患者の終末期の苦痛や家族の心境があまりにリアルに描かれていることです。
●医療従事者の何気ない一言や挙動が、患者家族の気持ちを大きく揺さぶること
●患者目線で情報を集めても、なかなか正確かつ有用な情報にたどり着けない現実と焦り
●透析患者の終末期のしんどさと、それに寄り添う家族の大変さ
このような精緻な描写が可能なのは、著者がプロの作家だからでしょう。
著者の堀川恵子さんは、本書前半の主人公である男性の奥さんで、テレビ番組のプロデューサーであり、小説で受賞歴もある方です。
取材の徹底ぶりも見事で、医学情報も含め、その情報の正確さと丁寧さには驚かされました。
旦那さんの死後、実際に透析学会に参加して講演を聴いたり、病院に見学に行って話を聴いたりと情報の質と量は凄まじいです。具体的なHDのメニューやPDの透析液まで記載されていた点には驚きました。
 おちば
おちば医療ドラマや小説(たとえば『ライオンのおやつ』など)でも終末期の描写はありますが、ここまで患者の生活や心理的側面+医学的側面を客観的な記録として残しているものは初めてなのではないでしょうか。
あとがきで「この文章はいわば献体である」という表現がありますが、まさに1人の症例を解剖するレベルで詳細な医学情報をまとめているような細かさでした。
② 透析患者の緩和ケア:「ボランティア」である理由
本書で著者は、終末期まで夫の介護を続け、大変な苦労を経験されました。
それにもかかわらず、結論として「透析患者の終末期は雑に扱われている。だから医師はもっとちゃんと見ろ!」といった単純なものになっていない点が特筆すべきポイントです。
現在の日本では、透析に精通した緩和医の不足や診療報酬の欠如などの理由で、透析患者の緩和ケアシステムが十分に整っていません。透析専門医ですら、不十分な知識のままクリニックを開いているケースもある中で、緩和ケアの専門知識を持つ医師はさらに限られています。
現状では、緩和ケアの診療報酬は「がん患者±心不全」に限定されており、透析患者の緩和ケアは事実上ボランティアのような状況です。日常診療の忙しさの中で、診療報酬がつかない緩和ケアやACP(アドバンス・ケア・プランニング)に時間を割くことの難しさについても言及されていました。



ぼく自身、終末期の近い患者さんとの面談を行っていますが、学会発表や論文の実績にはならず、給与にも反映されません。それでも必要だからこそ続けています。ただ、大学病院などの大規模施設では、さらに忙しいため難しいかもしれません。
また、本書では多くの医師への取材を通じて、「透析患者の終末期緩和マニュアル」が確立されていない現状が指摘されています。
終末期の診療は「お金にならない」ため、製薬会社などの支援を受けづらく、その結果、ガイドラインの策定や臨床研究も進んでいないのです。
本書は「医師 vs 患者」の二項対立ではなく、患者側が知っておくべき情報も伝えてくれている点が特徴的でした。それに、驚きと同時に深い学びを得ました。
③ 腎代替療法(腎移植、血液透析、腹膜透析)の全てを学べる1冊
この本は、腎代替療法について知りたい初学者や患者さんにとっても非常に有用な本です。
著者の旦那さんは、末期腎不全で血液透析を受けていますが、途中で腎移植を行われ透析を離脱、その後は再度血液透析導入になり、亡くなります。腹膜透析という選択肢を知るのは亡くなった数年後でしたが、詳しい医師に話を聞き、かなり細かいところまで理解された上で文章にまとめてくれています。
日本の透析患者さんの90%以上が血液透析(HD)を受けていますが、HDは必ずしも最後まで続ける必要はありません。
HDは週3回病院へ行く手間があるのに加え、血圧の乱高下が起きやすく、患者さんや介護者の精神的・肉体的負担が大きいです。食事が少なくなってきたとしても透析が回る限りは最後まで透析し続けます。最後は合併症を起こして病院で亡くなることが多いです。
一方で、腹膜透析(PD)は、導入時にカテーテルの挿入手術(多くは全身麻酔)が必要という一面はありますが、それさえ乗り越えれば、受診回数は少なく病院での拘束時間は少ないです。腹膜を介して数時間かけた毒素の除去、水分の除去をゆっくりおこなうため、血圧の乱高下の少ない「からだにやさしい透析」と言えます。もし食事量が少なくなってきた場合も、液の交換回数を減らすなどして全身状態にあった条件に変更することもできます。患者さんや家族さんの都合によって柔軟にスケジュールを変えられるため、在宅や緩和医療との親和性も高いです。
HD患者さんもPDに変更することで、緩和的にお看取りに持っていくことができる例も一定数あります。
しかし、透析室の医師や看護師でさえ、このことを知らない人が多いのが現実です。また、知識としては知っていても、地域のインフラによってPD導入が難しいことも多いです。
そのため、ある地域ではPDを積極的に導入しているのに対し、別の地域ではHDのみを行っているといった偏りも生じています。
本書は、ざっくりと言うならば、「HDを最後まで行ってつらい終末期を迎えるのではなく、PDに変更することでより穏やかな最期を迎えられるのではないか」というメッセージを込めた締めくくりになっています。
PDでの終末期(いわゆるラストPD)という選択肢さえ知っていれば、血液透析患者さんの中でも一定数は、命の締めくくりを穏やかなものにできる可能性があります。
本書を読んでいく中で、透析医は、HDを惰性で漫然と続けるのではなく、PDへの変更も適宜検討する必要があると再認識できるはずです。
まとめ
『透析を止めた日』は、自分の診療を振り返る良いきっかけとなる一冊でした。
あとがきで、腎臓学会のトップともいえる南学先生が「勉強になった」と述べていたように、この本を読んで学びがない医療従事者はいないはずです。
透析に関わる医師として、医学書や論文を読むよりまず、この本を確実に読んでおきたい一冊だと感じました。
PDは、HDとは異なり、患者さん中心の治療です。
看護師さんや技師さん、介護者さんと協力して自宅や施設で治療していただくことが必要なため、機械的にすすめることができるHDと比べると複雑で、いわば「手間がかかる」治療であると言えるでしょう。
ただ、確実にQOLは上がる症例が一定数いるはずです。今後も需要は増え続けると思われるため、きちんとPD導入できる患者さんへは情報提供をおこない、知識をつけるだけでなく、スタッフ育成や近隣病院との連携など、PDできる環境つくりをしていきたいと強く感じました。
みなさんも、ぜひ一度手にとって見てくださいね。
■関連する本
「ライオンのおやつ」
ホスピス入所した若年女性の目線で描かれる物語です。
近づいてくる死と向き合い葛藤する中で、最後は受容していく様が描かれています。周りの入所されている方たちが亡くなっていくエピソードが本当に様々で、ひとりひとりの一生に様々なドラマがあるのがわかります。(自分は、物語の最中に出てきた小さい子のエピソードで当直明けに自宅で号泣してしまって…いまも鮮明に記憶に残っています)
「メメントモリ」という言葉もありますが、死を意識することで今の生を大事にできるようになる1冊です。
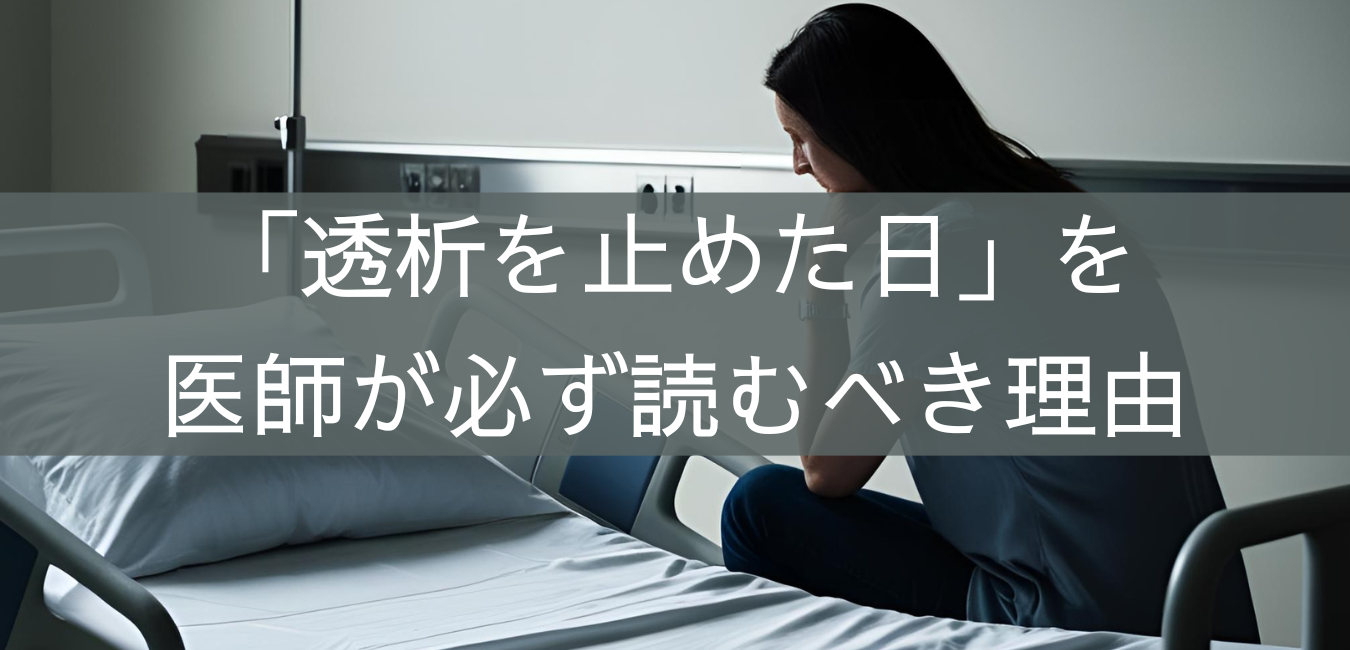



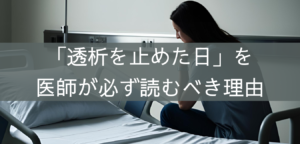

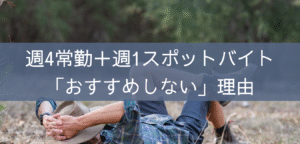
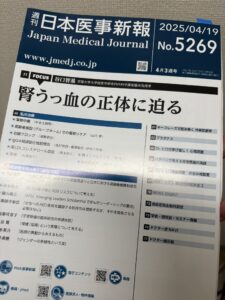


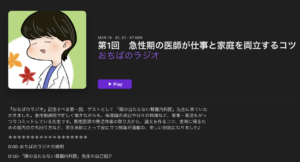

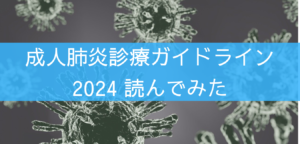

コメント